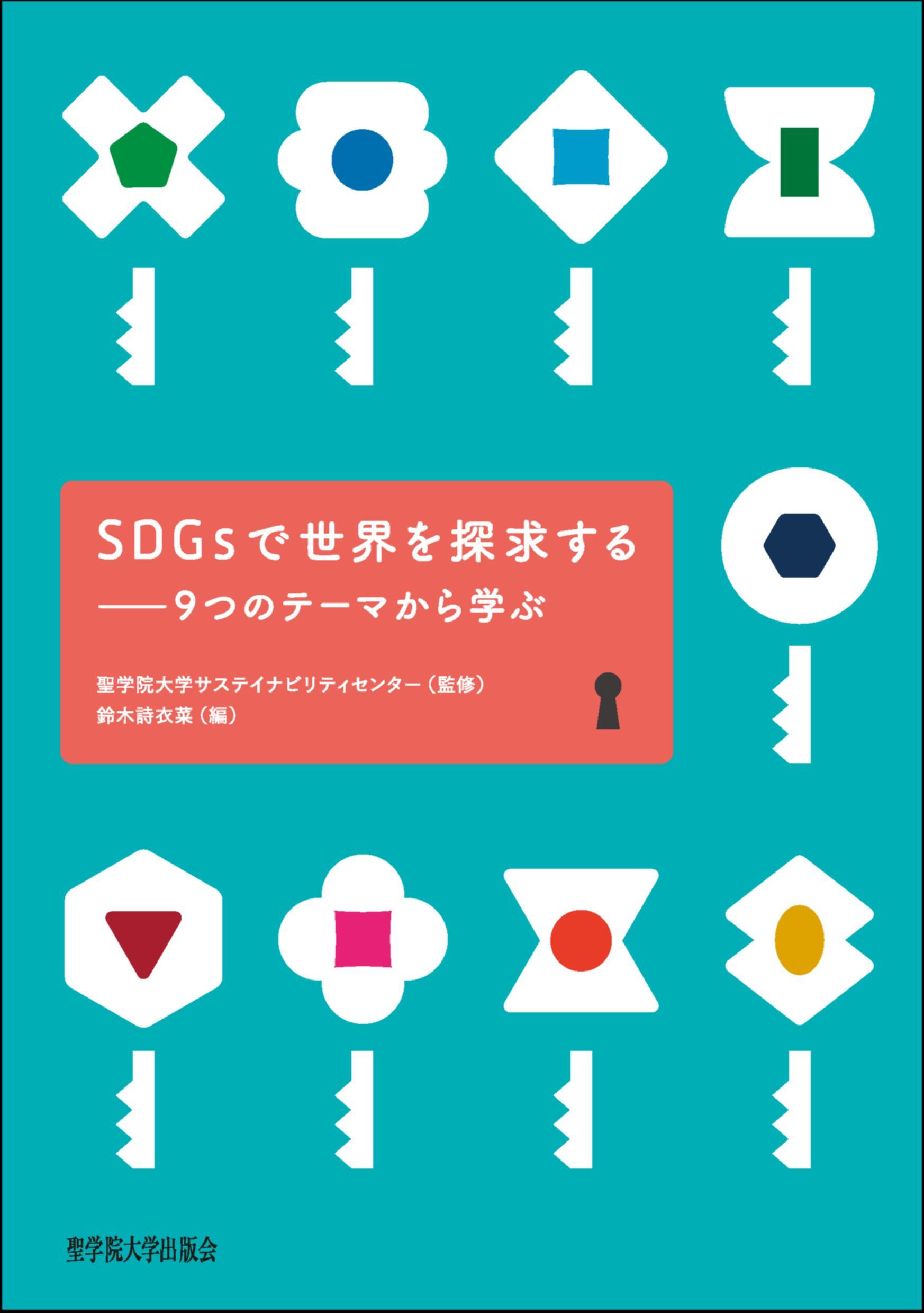
| 編著者 | 聖学院大学サステイナビリティセンター 監修 鈴木詩衣菜 編 |
|---|---|
| 判型 | A5判 |
| ページ数 | 236 ページ |
| 製本 | 並製 |
| 発行日 | 2025年04月 |
| ISBN | 978-4-909891-18-1 C0030 |
| 定価 | 2,640円(10%税込) |
| 在庫 | あり |
インターネットでのご購入はこちら
内容紹介
音楽、美術、文学の観点も盛り込まれた本書は、学際色豊かなSDGsの世界が展開されており、SDGsの17の目標に直接関わるテーマから、各目標と横断的に関わるテーマなどを概観することができる「最初の専門書」。
編著者プロフィール
鈴木詩衣菜(すずき・しいな)
聖学院大学政治経済学部准教授、サステイナビリティセンター所長。上智大学大学院地球環境学研究科博士後期課程修了。博士(環境学)。専門は、国際法、国際環境法。主な研究関心は、環境紛争の効果的な解決と環境条約の実効性の確保。主な著書に『国際法学の諸相』(分担執筆、信山社、2015年)、『水辺を知る――湿地と地球・地域』(編共著、朝倉書店、2023年)などがある。
西海洋志(にしかい・ひろし)
横浜市立大学国際教養学部准教授。東京大学大学院総合文化研究科グローバル共生プログラム博士後期課程単位取得退学、博士(グローバル研究)。専門は、国際政治思想。主な著書に、『保護する責任と国際政治思想』(国際書院、2021年)、『地域から読み解く「保護する責任」——普遍的な理念の多様な実践に向けて』(共編著、聖学院大学出版会、2023年)などがある。
長嶋佐央里(ながしま・さおり)
聖学院大学政治経済学部准教授、地域連携・教育センター副所長。関西学院大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程後期課程単位取得満期退学。博士(経済学)。専門は、財政学、地方財政、社会保障の財政。主な論文:「日本の市町村における児童福祉費の扶助費の動向分析」『経済環境研究』第8号、2019年、「個人住民税の非課税限度額に関する考察」『経済学論究』第67巻第4号、2014年。
若原幸範(わかはら・ゆきのり)
聖学院大学政治経済学部准教授。北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。専門は社会教育学。主要著書に、宋美蘭編著『韓国のオルタナティブスクール――子どもの生き方を支える「多様な学びの保障へ」』(分担執筆、明石書店、2021年)、鈴木敏正, 朝岡幸彦編著『社会教育・生涯学習論――すべての人が「学ぶ」ために必要なこと』改訂版(分担執筆、学文社、2023年)など。
川田虎男(かわた・とらお)
埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授、聖学院大学非常勤講師、同大ボランティア活動支援センター/サステイナビリティセンターアドバイザー。NPO法人ハンズオン埼玉代表理事。社会福祉士。立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科博士後期課程修了。博士(社会デザイン学)。専門は、市民活動・ボランティア、地域福祉。主な著書に、李永淑編『モヤモヤのボランティア学――私・他者・社会の交差点に立つアクティブラーニング』(分担執筆、昭和堂、2023年)などがある。
小沼聖治(おぬま・せいじ)
聖学院大学心理福祉学部准教授、精神保健福祉士。大正大学大学院人間学研究科博士後期課程修了。博士(人間学)専門は、精神保健福祉、ソーシャルワーク、ソーシャルアクション。主な研究関心は、精神保健福祉領域におけるソーシャルアクションの実践モデル形成やメンタルヘルスの普及啓発。主な著書に『ソーシャルアクション・モデルの形成過程――精神保健福祉士の実践を可視化する』(法律文化社、2024年)、鈴木孝典, 鈴木裕介編著『図解でわかるソーシャルワーク』(分担執筆、中央法規出版、2023年)などがある。
江崎聡子(えざき・さとこ)
聖学院大学人文学部欧米文化学科准教授。専門分野はアメリカ美術、アメリカ視覚文化。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。著書に『エドワード・ホッパー作品集』(東京美術、2022年)、『デリシャス・メトロポリス――ウェイン・ティーボーのデザートと都市景観』(創元社、2024年)、『描かれる他者、攪乱される自己――アート・表象・アイデンティティ』(共著、ありな書房、2018年)などがある。
久保田 翠(くぼた・みどり)
聖学院大学人文学部准教授、サステナビリティ推進センター副所長。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、東京大学大学総合文化研究科表象文化論コース修士課程修了、同コース博士課程単位取得満期退学。主な著書に、久保田翠編曲『ピアノで弾くチャーチソング――讃美歌・聖歌:中級』(カワイ出版、2021年)、『小学校音楽科の指導法』(編共著、ヨベル、2024年)、主な作品に、CD『later』(ombrophone records、2020年)など。https://midorikubota.net/
木下綾子(きのした・あやこ)
聖学院大学人文学部准教授。明治大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。専門は、平安文学。主な研究対象は、物語文学や漢詩文を中心とした日中の文学・歴史資料の比較、読解。主な業績に「『源氏物語』と「長恨歌」「長恨歌伝」」(漢文教室編集部編『漢文教室』206号、大修館書店、2020年)、「光源氏と冷泉帝――「天に二日無し」という典拠と準拠」(中古文学会編『中古文学』95号、中古文学会、2015年)など。
髙橋愛子(たかはし・あいこ)
聖学院大学名誉教授。国際基督教大学行政学研究科博士後期課程修了、博士(学術)。
専門は政治学、政治思想史、特にカール ・シュミット、ヘルマン ・ヘラーを中心とするワイマール期政治思想、法思想。主要著者として『政治権力の民主的正当性と〈合法性〉――シュミットとヘラーの法廷対決』(風行社、2023年)、姜尚中・齋藤純一編『逆光の政治哲学――不正義から問い返す』(分担執筆、法律文化社、2016年)など。
正森涼子(まさもり・りょうこ)
聖学院大学サステイナビリティセンター・コーディネーター(専門職)。英国サセックス大学大学院国際教育開発学修士課程修了。修士(国際教育開発学)。持続可能な開発のための教育(ESD)や国際教育開発分野において国連機関での勤務経験をもつ。
芦澤弘子(あしざわ・ひろこ)
聖学院大学ボランティア活動支援センター・ボランティアコーディネーター(専門職)。立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科博士課程前期課程修了。修士(社会デザイン学)。旅行会社、NPO支援センターを経て現職。
上記内容は本書刊行時のものです。
目次
はじめに(鈴木詩衣菜)
第1章 政治×平和×SDGs――他者と共に未来をつくるということ(西海洋志)
第2章 経済学・財政学×地球環境・貧困×SDGs――問題解決の政策手法としての税制(長嶋佐央里)
第3章 国際法×自然環境×SDGs――環境問題の諸相とルール(鈴木詩衣菜)
第4章 教育×社会×SDGs――持続可能な社会を目指す地域社会教育(若原幸範)
第5章 ボランティア×地域× SDGs――SDGs 実現に向けてボランティアが果たす役割(川田虎男)
第6章 社会×福祉×SDGs――障害者福祉とメンタルヘルスを中心に(小沼聖治)
第7章 ジェンダー×イメージ×SDGs――視覚文化にジェンダーの視点を取り入れると何が見えてくるのか(江崎聡子)
第8章 音楽×SDGs―創作の持続可能性と「遊び」(久保田 翠)
第9章 日本文学×SDGs――『枕草子』の「聖代」観――中宮定子と藤原伊周による一条天皇の教導(木下綾子)
コラム1 好きなこと×地球規模課題×SDGs――自分の興味・関心からはじめるSDGs(正森涼子)
コラム2 ボランティア×SDGs――ボランティア・まちづくり活動助成金の事例から(芦澤弘子)
刊行に寄せて 所与、選択、そして想像すること――今こそSDGsという国際的約束を前へ(髙橋愛子)
